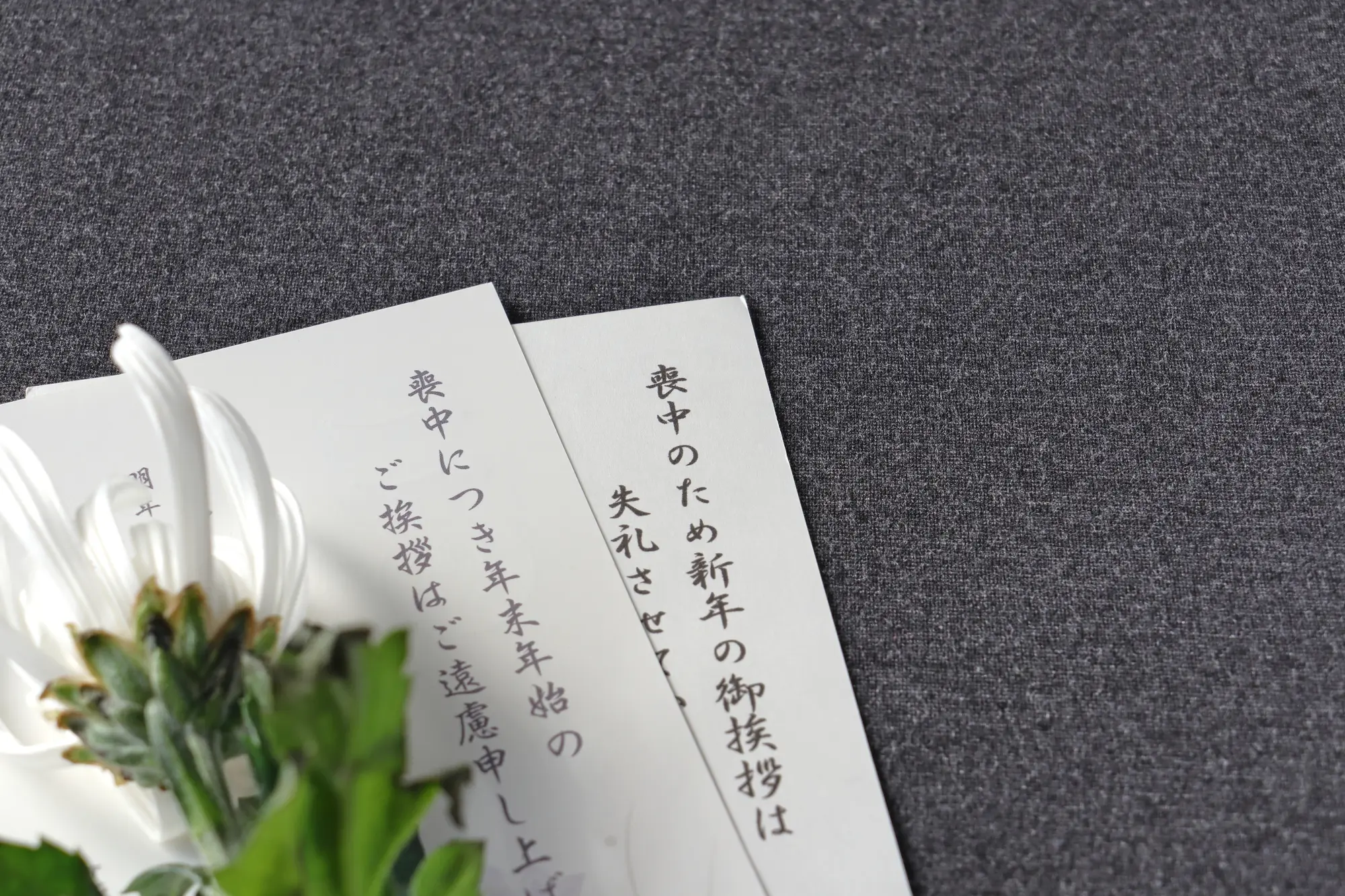メニュー
公開日:

・最高100歳までの保障 85歳10ヶ月まで申込可能
・加入審査も告知だけの簡単手続き
・豊富な13プランを用意 保障は50万円から可能
・死亡保険金は原則翌営業日に、支払います!
もしものときの葬儀への備えなら
葬儀保険「千の風」にご相談ください
もしものときの葬儀への備えなら
葬儀保険「千の風」にご相談ください
・最高100歳までの保障 85歳10ヶ月まで申込可能
・加入審査も告知だけの簡単手続き
・豊富な13プランを用意 保障は50万円から可能
・死亡保険金は原則翌営業日に、支払います!
葬儀保険「千の風」のコラムのページをご覧いただきありがとうございます。
一般的に葬儀が終わると「精進落とし」と呼ばれる会食がおこなわれます。なぜ葬儀後に遺族や親族が集まって食事をするのでしょうか?精進落としの意味やマナー、精進落としの流れ、挨拶の例などを紹介しています。
目次

精進落としとは、葬儀や初七日法要あとに遺族や親戚、故人の友人、僧侶が参加しておこなわれる食事会です。地域によっては葬儀のあとではなく、火葬中におこなわれることもあります。
昔は故人が亡くなり四十九日をむかえるまで、遺族は魚や肉などを使わない精進料理を食べていました。精進料理を食べることで故人を弔い、無事に極楽浄土へたどりつけるように、と願っていたのです。
四十九日の忌明けの際に、久しぶりのごちそうとして肉や魚を口にしていました。これを「精進落とし」と呼んでいました。
ところが今、かつての精進落としの意味合いは薄れています。葬儀のあとに遺族、親族、僧侶をねぎらうための食事会が、現在の一般的な認識です。
精進落としですが「お斎(とき)」「精進明け」「精進上げ」など、地域や宗派によって呼び方に違いがあります。
精進落としは葬儀のあとや火葬中に振る舞われる食事をさし、通夜振舞いはお通夜のあとに振る舞われる食事を意味します。通夜振舞いは故人の思い出を語る場としてもうけられ、遺族や会葬者への感謝の気持ちや故人との最後の食事、お清めの意味も込められます。
精進落としはお膳で個別に用意するケースが多いのですが、通夜振舞いは参加する人数をあらかじめ特定できません。そのため大皿で用意され、オードブルやサンドイッチ、おにぎり、煮物などが用意されることが多いです。
精進落としは自宅や葬儀会場、料亭やレストランでおこなうケースがほとんどです。地域によっては火葬場で精進落としをおこなうこともあり、この場合は火葬場の待合室などでおこないます。
食事は葬祭場が用意してくれることもありますし、喪主が仕出し弁当を用意するケースもあるため、事前に確認しておきましょう。懐石料理を選ぶのであれば料亭やレストランが最適です。
精進落としは読経をしていただいた僧侶と遺族、親戚が参加するのが一般的です。ほかにも故人の親しい友人や会社関係者の方々に声をかけることもあります。
火葬場で精進落としをおこなう場合は、僧侶や親族以外にもお骨上げまで立ち会ってくださった方も参加することが多いです。
精進落としの一般的な席順は、上座に読経をしていただいた僧侶、次に友人知人、会社関係の方、親族の順に着席していただきます。遺族や喪主は末席に座るのがマナーです。
一般的に精進落としで振る舞われる料理は、一人一膳の仕出し弁当、または懐石料理です。お寿司やオードブルなども振る舞われます。
ただ精進落としは弔事の会食ですから、鯛や伊勢海老などお祝いの席で使用されることが多い食材の使用は避けましょう。地域によっては慶事で使用される特定の食材があるので注意してください。

始まりの挨拶は喪主や親族代表がおこないます。無事に葬儀を終えることができた感謝の言葉、今後のご厚誼をお願いする言葉、食事を勧める言葉などを含めた挨拶をしましょう。
【挨拶文例】
本日はお忙しい中、故〇〇の葬儀にお集まりくださいましてありがとうございました。皆さまのお力添えのおかけで無事に葬儀を終えることができました。今後も亡き父同様、変わらぬお付き合いをお願いいたします。ささやかではございますが精進落としを用意いたしました。お時間の許す限りおくつろぎください。本日は誠にありがとうございました。
喪主の挨拶に続き、献杯がおこなわれます。献杯は故人に対して敬意を示し杯を差し出す行為です。
献杯の挨拶は遺族・親族のほか、故人と親しい知人や会社の上司などが担当します。喪主以外の方にお願いする場合は、事前に声をかけておくのがマナーです。
献杯時の挨拶は葬儀に参加していただいたことに対する感謝の気持ち、故人との関係がわかるエピソード、献杯の掛け声の流れが一般的です。
【挨拶文例】
皆さま、本日はお集まりいただきありがとうございました。私は〇〇(故人)の友人の〇〇です。〇〇さんとは学生時代からの長い付き合いで、明るく気さくな人柄がとても印象的でした。悩み事があると〇〇さんに相談にのってもらい、何度もよいアドバイスをもらいました。彼の明るい笑顔や一緒に旅行に行った思い出が、今でもはっきりと心に浮かびます。
大好きな〇〇さんを偲んで皆様と献杯できることを、本当にうれしく思っております。
それでは献杯させていただきます。献杯。
献杯後に合掌または黙とうをおこない、故人を偲ぶ場合があります。宗教や宗派、また地域の風習などにより違いがありますので、事前に確認しておきましょう。
会食では、喪主や遺族が親族以外の参加者を順番にまわり、お酌をすることが多くあります。一般的な会食の所要時間は数時間とされていますが、近年は精進落としの所要時間が短縮される傾向にあり、約1~2時間でお開きとなる傾向があります。

食事が終わると、喪主、または親族代表が挨拶をして精進落としは終了です。僧侶に出席していただいた場合は、挨拶が終わった段階でお布施を渡します。
挨拶には精進落としに参加していただいた感謝の言葉、今後のご厚誼をお願いする言葉などを含めます。
【挨拶文例】
皆さま、本日はお忙しいなか、最後までおつきあいいただきありがとうございました。つかの間でしたが、これにてお開きとさせていただきます。どうか今後ともよろしくお願いします。本日は誠にありがとうございました。
精進落としは、読経をしていただいた僧侶にも声をかけるのがマナーです。料理は他の出席者と同じメニューで問題ありません。
もし僧侶が精進落としに同席されない場合は、御膳料としてお金を包んでお布施と一緒にわたします。また、一般的な御膳料の金額は5千円~1万円ですが、もし懐石店やホテル、レストランなど高級店で精進落としをおこなった場合は、相場より高めの1万円~2万円になります。
御膳料については以下の記事も参考にしてみてください。
参考:「御膳料の書き方とは?マナーや渡し方についても解説!」
精進落としの際には、故人にも他の参加者に振る舞うお膳と同じものを「影膳」としてお供えします。ただし浄土真宗では故人は確実に往生し仏となって子孫を導く、という即得往生の発想があります。影膳は「故人が無事に極楽浄土にたどり着けるように」という願いが込められていますが、浄土真宗にはこの発想がないため、影膳は必要ありません。
精進落としでは始まりの挨拶・献杯の挨拶・終わりの挨拶と節目に応じて挨拶がおこなわれます。喪主か親族代表がおこなうケースも多いのですが、もし故人の知人や上司にお願いする場合は、事前に連絡し了解をもらっておきましょう。
直前にお願いされると、当事者も戸惑ってしまいます。また一時的にパニックになり、忌み言葉や重ね言葉を言ってしまうリスクもあります。
忌み言葉とは不幸を連想させてしまう言葉で、特に葬儀や精進落としなど弔事には避けなければなりません。例としては「重ね重ね・いろいろ・ぜひぜひ」など、同じ言葉を2度使う重ね言葉です。
重ね言葉は不幸が重なるとイメージされるため「加えて・さらに・ぜひとも」などの言葉に言い換えます。ほかにも「死ぬ・急死・生きていた頃」など生きる・死ぬをストレートに表現する言葉も厳禁です。
「ご逝去・ご生前・お元気だった頃・急逝・突然のこと」など、遺族を傷つけない言葉に言い換えるのがマナーとなります。
精進落としではお酒を飲んでも構いません。ただし、お酒がはいるため、宴会のようにダラダラ長引く可能性があるため注意してください。
あらかじめ終了時間を決めておき、時間になったら終わりの言葉をかけて終了させます。遺族や参加者の体調や疲労を考え、長引かせないのが無難です。

精進落としは参加人数が把握しやすいため、一人一膳で仕出し料理などを準備しています。欠席する場合は喪主が仕出し料理をお弁当にして用意するケースもあるため、事前に連絡しておくと無難です。
途中で退席する場合は目立たないように遺族に声をかけます。
精進料理が目の前に用意されていても、献杯の挨拶が終わるまでは料理に手を付けないのがマナーです。挨拶前に食事を食べると「非常識な人」と思われてしまいます。
献杯時は隣同士の方と杯をぶつけて音を出さないようにしましょう。献杯と乾杯では意味が違います。
献杯では、杯を目線の高さまで持ち上げる程度で十分です。大きな声を出して「献杯!」と言う必要もありません。
故人との思い出話や遺族を励ます話題はよいのですが、故人の死因や遺産状況などを尋ねるのはマナー違反です。遺族の気持ちを考えて話題選びをするようにしましょう。
精進落としはあくまで故人を偲ぶ時間です。内輪で騒いで楽しむ場所ではありません。
お酒が入ると宴会気分になり、大声を出したり遺族に絡むなど迷惑行為に走ることもあります。お酒の飲みすぎには注意しましょう。
精進落としの費用相場は約5千円~1万円です。あまりに安い料理では品数が減り、見た目もかなり悪くなります。今後のお付き合いもあるため、相場なりの料理を用意しましょう。
また金額のずれをなくすために、あらかじめ参加人数を正確に把握しておくことが大切です。
遠方から葬儀に来ている、用事がありどうしても精進落としに参加できない方もいるでしょう。このような場合はお弁当を用意することが望ましいです。お弁当が用意できないときは御膳料を包むなどして対応しましょう。
持ち帰りの対応ができるところもありますが、会場によって異なるため、事前の確認が必要です。また自宅で精進落としをおこなう場合は仕出し料理を用意するケースが多いため、持ち帰り箱で用意された料理であれば可能です。

参列してくれた方々へ感謝を伝えるためにも、精進落としをおこなうのがマナーです。また精進落としは、故人の安らかな旅立ちや極楽浄土へたどり着けるようにとの願いも込められています。
浄土真宗、神道、キリスト教などそれぞれで精進落としの呼び方や内容が異なります。浄土真宗は念仏を唱えれば成仏できるとされており、四十九日の概念がありません。
精進落としと同じ会食はありますが、浄土真宗の場合は「お斎(おとき)」と呼びます。
また神道でも葬儀直後に遺族や親族が集まる会食がおこなわれますが、これは「直会(なおらい)」と呼ばれています。
キリスト教では精進落としにあたる会食はありませんが、会葬者や葬儀を手伝ってくれた方にお菓子とお茶を振る舞い、労をねぎらうケースがあります。
葬儀後や火葬中におこなう精進落としですが、参列者が少ないなどの理由で精進落としをおこなわない場合もあります。この場合は、返礼品とは別にお弁当、または御膳料を手渡しましょう。
読経をお願いした僧侶には、御膳料とお布施を渡します。
精進落としは、葬儀に足を運んでくださった僧侶や親族、会葬者に感謝を示し、故人の冥福を願う場としてもうけられています。また故人の思い出話をしたり、遺族とさまざまな話をする役割もあります。
ただお酒が入るため羽目を外して騒ぐ、泥酔するなど遺族に迷惑をかける行為は厳禁です。精進落としは故人を偲び、その冥福を祈る会食であることを理解しておきましょう。
精進落としの意味やマナーを知ることで、遺族、会葬者ともに穏やかな気持ちで過ごせるでしょう。