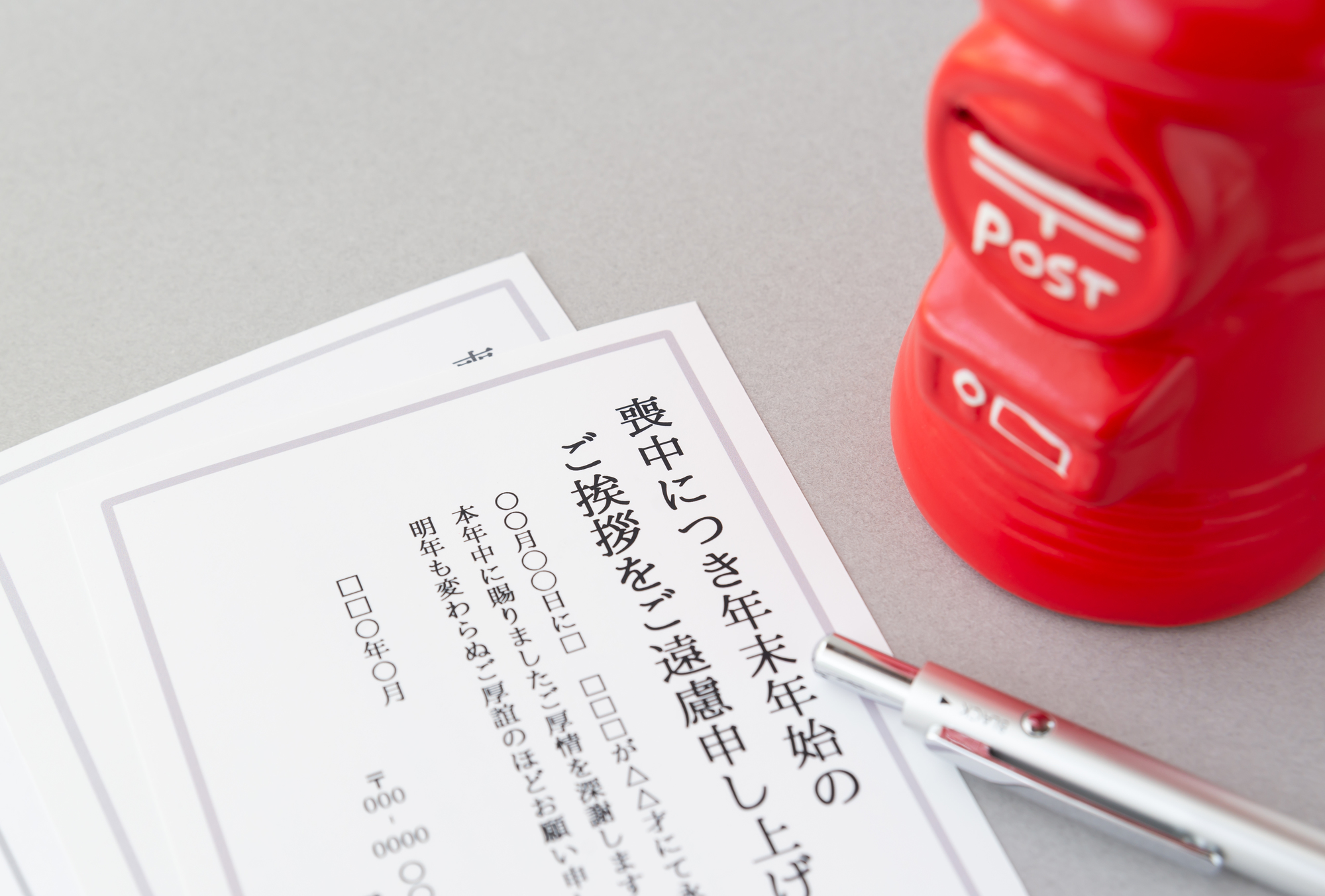メニュー
公開日:

・最高100歳までの保障 85歳10ヶ月まで申込可能
・加入審査も告知だけの簡単手続き
・豊富な13プランを用意 保障は50万円から可能
・死亡保険金は原則翌営業日に、支払います!
もしものときの葬儀への備えなら
葬儀保険「千の風」にご相談ください
もしものときの葬儀への備えなら
葬儀保険「千の風」にご相談ください
・最高100歳までの保障 85歳10ヶ月まで申込可能
・加入審査も告知だけの簡単手続き
・豊富な13プランを用意 保障は50万円から可能
・死亡保険金は原則翌営業日に、支払います!
葬儀保険「千の風」のコラムのページをご覧いただきありがとうございます。
故人を見送るときに欠かせない死装束ですが、宗教や宗派によって違いがあります。あらかじめルールを知っていればいざというときに慌てずにすみます。また故人が、特定の服を死装束として指定されている場合にも役立つ内容です。ぜひご覧ください。

死装束(しにしょうぞく)とは、亡くなった方に着用させる衣装を指します。日本だけではなくさまざまな国で、死装束の種類があります。
日本では人が死ぬと、その人物はこの世からあの世に旅立つという発想があり、それにふさわしい衣装として死装束を用意するようになりました。死装束は基本的に白帷子(白い着物)ですが、白色である理由は諸説あります。
古来から修行者や巡業者が白い着物を着用していたこと、白色が誕生を意味する紅(赤色)と反対の色であることから「死」を意味すると考えられていました。そのため白い死装束を着せてあの世に送り出すのです。
白色は死を連想させる色ですが、同時に清浄な色でもあります。一切汚れのない白色を身に着けることで、生前の穢れを清めてあの世に旅立てるようにという願いが込められています。
基本的に死装束は、葬儀社と遺族が相談して準備します。一般的な白帷子以外にもエンディングドレスや故人の思い出の洋服など、特別な服装を着せたいという場合もあるでしょう。
どのような死装束を着用させるにしても、一度葬儀社に相談するのが基本です。勝手に着用させるとトラブルのもとになる可能性があるため注意しましょう。
仏教における死装束は経帷子が一般的です。この世への執着や成仏の妨げを連想させる玉止めや返し縫をせずに作られています。
着物には真言や経文が書かれていますが、これは仏様に守られながらあの世に旅立つことを意味しているのです。ただ死後硬直でご遺体の腕が動かない場合は、ご遺体に経帷子をかけることもあるようです。
現在では宗教宗派にとらわれず、常識の範囲であれば一般的な死装束を着用しなくてもよい、という発想が定着しつつあります。故人のお気に入りの服を着用させお見送りするスタイルを取り入れるケースもあり、特に着物は着用しやすい死装束です。
生前お気に入りだった私服を、死装束として着せる場合もあります。エンディングノートで「ピンクのドレスを着用して旅立ちたい」など、生前の希望があればその意思が尊重される傾向です。
ただ死後硬直後は着せにくい場合もあるため、死後の早い段階で着せておく、伸縮性のよい素材を選ぶ、サイズが大きい着せやすいものを選ぶとよいでしょう。

神式における死装束は神衣(かむい)が一般的で、神主のような死装束を用意します。男女で形式が異なる点に注意してください。
男性の場合は公家が着用する白い狩衣(かりぎぬ)を着せ、黒い烏帽子(えぼうし)を頭に装着します。手には笏(しゃく)を持たせます。
女性の場合は白い小袿(こうちき)を着用し、手には扇を持たせるのが基本です。
キリスト教では、特定の死装束はありません。生前好んで着用していたスーツやドレスを着用するのが一般的です。
近年日本でもこの文化が広まり、死装束としてエンディングドレスを選ぶケースが増えています。男性の場合、黒のスーツなど落ち着いた色の洋服も好まれます。
ここでは装飾や小物についての意味や身につける場所などの、基本情報をご説明しています。
額の部分につける三角形の形をした頭巾です。これは死後に閻魔様に謁見するときの正装と考えられています。
ほかにも仏様の弟子であることを示すため、また極楽浄土の旅で顔を隠すためなど諸説あるようです。
腕の上部から手の甲までを覆う防具です。巡業者や修行僧が着用していました。
三途の川を渡るとき、代金となる六文銭を納める袋を指します。現在は小銭(金属)を入れて火葬ができないため、紙に印刷された六文銭を使用するケースが多いようです。
日よけや雨よけのため、頭にかぶる笠を意味します。ただし、ご遺体に笠を被せると顔が見えなくなるため、副葬品として棺の中に納めます。
脛(すね)に巻いて足を保護するのが脚絆です。手甲と同じく防具の一種で、脛あての意味合いがあります。
足袋は現在の靴下を指します。極楽浄土への長い旅に備え、安心して歩いてもらいたいという意味合いがあります。
数珠は経文を唱えるときに使用する法具の一種です。数珠には煩悩を断ち切り、心身を清める意味があります。
生前使用していた数珠があればそれを使用しますが、金属製など燃えにくい素地のものは避けます。遺体の手に持たせるケースが多いのですが、それができないときは頭陀袋に納めます。

藁でできた草履は現在の靴に相当するものです。足袋と同じく足元をしっかり守り、長い旅でも安心して歩けるように、という願いが込められています。
足袋や草履と同じく、険しい道のりも杖を使って安心して旅してほしいという意味合いがあります。旅の途中で倒れないようにという配慮です。
杖は、故人と棺の間に添えるように納棺します。
現在では紙幣や硬貨は火葬できないため、印刷したものを持たせるケースが一般的です。
友引に葬儀をおこなうと、友人や家族が連れていかれると考えられており、それを避けるために人の代わりとして入れていたものが友引人形です。
火葬の関係により、燃えやすい小さいぬいぐるみであることが望ましいでしょう。葬儀社によっては、事前に用意してくれることもあります。
死装束は納棺前に着せるのが一般的で、現在は葬儀社の専門スタッフが着用させるケースが多い傾向にあります。ただ最低限の襟のルールや帯の結び方について知っておくと役立ちます。チェックしていきましょう。
通常、着物を着用するときは襟を右前にするのが常識です。ただ死装束は襟を左前にします。これは生者と区別するためと言われています。
ほかにも奈良時代に定められた法律で、身分の高い方は左前で着物を着用するルールがありました。高貴な身分の方を真似、来世は高い身分の者に生まれ変わってほしいという願いが込められています。
帯はかた結びにし、蝶結びが縦結びになるようにします。一般的な蝶結びはほどけやすく、何度も締めなおす必要があります。
弔事は何度も起こってほしくないため、ほどけにくいかた結びと縦結びを使用します。
死装束の着用は、納棺前が一般的です。葬儀社によっては湯灌(ゆかん)をおこなうことがあります。
湯灌とはご遺体をお湯で洗い清める儀式になります。死装束は湯灌後に着用するのが基本です。
棺には故人の愛用したものを入れてもよいとされています。ただ棺に入れられない物もあるため注意してください。
思い出の品として残したいなら、骨壺に直接納めるのがよいでしょう。

以下の関連記事もご参考ください。
「納棺とは?儀式の流れや費用、服装や時間など詳しく解説」
仏教では、あの世にいった方は「極楽浄土を目指して旅立つ」と考えられています。そしてその旅の途中で修行をおこない、悟りを開くと考えられているのです。
そのため修行僧や巡業者のような死装束を着用し、長い旅に送り出します。
考え方は仏教と同じですが、一部の信者はあらかじめ死装束を用意しているケースもあります。四国四十四か所霊場を巡業し、経帷子に御朱印を押してもらうなどして死装束を用意します。
真言宗は空海(弘法大師)が開祖であるため「南無大師遍照金剛」(弘法大師に帰依しますの意味)という経文が、死装束に書かれているのも特徴です。
日蓮宗も考え方は仏教をベースとしていますが、経帷子には「南無妙法蓮華経」(なむみょうほうれんげきょう)というお題目が書かれています。本尊である十界曼荼羅(じっかいまんだら)が描かれた経帷子も使用されます。
日蓮宗ではお寺の行事で使用する行衣(ぎょうい)を個人個人で持っており、愛用の行衣を死装束として着用することもあるようです。
浄土真宗では、亡くなった方はすぐに極楽浄土に行けると考えられています。そのため修行僧のような死装束は着用しません。
その代わり、故人が愛用していた洋服や着物を使用します。色も白色にこだわる必要はなく、着せ方も襟を右前で合わせて構いません。
神道では、亡くなった方は遺族を守る守護神のような存在になると考えられており、修行僧や巡業者のような死装束はふさわしくありません。男性には白い狩衣(かりぎぬ)と烏帽子を身につけ笏を持たせ、女性には白の小袿と扇を持たせます。
神職の方が着用する衣装に似た死装束を着せることで、子孫の守護神となるのです。

キリスト教には、死装束への細かい決まりごとはありません。そのため生前に気に入っていたスーツやドレス、洋服でよいとされています。
ただし遺体を覆う、服の上からかける生地は黒、ないしは白を選びます。副葬品として木製の十字架を手元に置くケースもあるようです。
無宗教の場合は特に決まりはなく、生前好んで着ていた服を使用します。ただ洋服の素材によっては火葬で燃えにくいケースもあるため、死装束として着用できる洋服かどうか事前に相談しておくとよいでしょう。
近年では故人が好きだった服装を着せる場合もありますが、遺族・親族から反対される場合もあるため事前に確認しておきましょう。喪主が独断で死装束を選ぶと、あとでもめるケースもあります。
また地域によっては死装束の風習が違うため、よくわからない場合は葬儀社のスタッフと事前に相談しておくと安心です。
亡くなると死後硬直のため腕が曲げにくい、関節が動きにくいなどが発生することがあります。そのため身体にぴったりフィットする洋服は、死装束としては向いていません。
無理に服を着せようとすると遺体を傷つける恐れがあるため、心配な場合は事前に葬儀社側に相談しましょう。
死装束の素材は、白木綿や白麻、リネン(亜麻布)などの自然素材であれば問題ありません。洋服にプラスチック素材が使われている、金属製のアクセサリーがついているなどすると火葬時にトラブルが起きる可能性があります。
葬儀社が用意する死装束であれば素材に問題ありませんが、遺族側が用意する場合は注意してください。
一般的に死装束は葬儀社が用意しますが、現在は故人が好きだった洋服やエンディングドレスを着用するケースも増えています。生前に「この衣装を死装束にしてほしい」と希望している場合は、できるだけ希望を叶えることが供養になるでしょう。
ただ火葬に適さない生地や着用させにくいデザインもあるため、葬儀社の方やほかの親族とも事前に打ち合わせをおこなうことが大切です。これは死装束だけの問題ではありませんが、一部の遺族の意向だけで葬儀を進めずに、事前に話しておけると安心です。